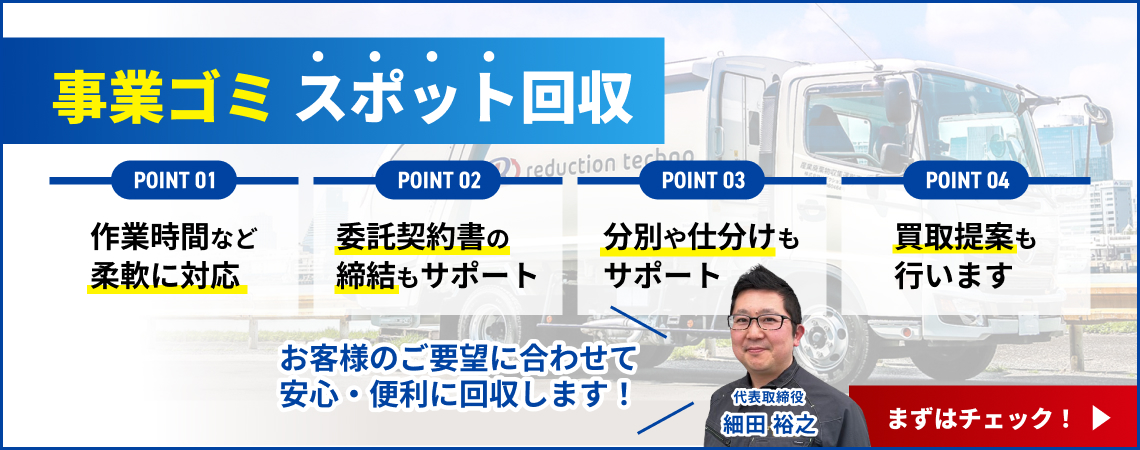コラム
産業廃棄物 2021.06.14
中間処理はなぜ必要?産業廃棄物の処理工程・最終処分との違いを徹底解説
環境環境貢献産業廃棄物SDGs
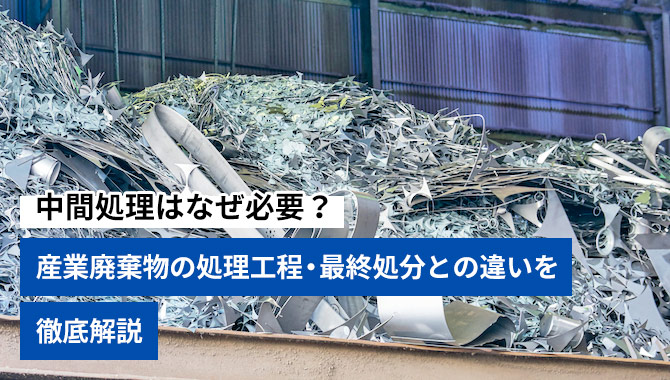
中間処理は、産業廃棄物を最終処分もしくはリサイクルしやすい状態にするための作業を指します。 しかし、「産業廃棄物を捨てているけど、処理工程について詳しく知らない…」という方も多いのではないでしょうか? そこで本記事では、中間処理を含む、産業廃棄物の処理工程にクローズアップ! 最終処分との違いや中間処理の必要性も解説します。
1.産業廃棄物が処理されるまでの流れ
産業廃棄物の処分と聞くと最終処分場での埋め立てをイメージする方も多いかもしれません。
しかし、排出事業者が出す廃棄物がすべて回収後そのまま最終処分場で埋め立てられるわけではありません。
産業廃棄物は、一般的に以下のように処理されます。
収集運搬 → 中間処理 → 最終処分
このように段階を踏んで処理することで、分別・減量をおこなっています。
2.中間処理とは?
中間処理とは、産業廃棄物を最終処分もしくはリサイクルしやすいように安全化・安定化・減量化する作業のこと。
中間処理を行う場所は「中間処理施設」と呼ばれており、受け取った産業廃棄物を種類ごとに選別したり、焼却や破砕、脱水などを行って減量化します。
つまり、中間処理は最終処分やリサイクルするための前処理といえます。
3.廃棄物処理の種類
産業廃棄物を処理する際には、主に2種類の方法があります。
1つは前項でご紹介した「中間処理」。
廃棄物を安全化・安定化・減量化して最終処分しやすい状態へと変える作業を指します。
中間処理はこれを安全な状態にするだけでなく、容量を減らすためにも必要な工程です。
もう1つの処分方法は「最終処分」。
埋め立てや海洋投入、リサイクルといった方法で処分します。
ただし海洋投入は、海洋汚染防止という観点から現在あまり行われていません。
4.中間処理と最終処分の違い
どちらも廃棄物処分に関わる大切な作業ですが、概要は全く異なります。
前項の解説のように、中間処理は最終処分の前段階で最終処分しやすいよう安全化・安定化・減量化する作業です。
対して、最終処分とはその名の通り、廃棄物を最終的に処分すること。
中間処理を行った後に最終処分場で埋め立てたり、リサイクルしたりして有価物に変えることを指します。
中間処理は最終処分の前段階であり、それぞれ別物と覚えておきましょう。
5.中間処理の主な工程
続いて、中間処理の主な工程をご紹介します。
ひとくちに中間処理といっても、減量化・減容化・選別と方法は様々です。
中間処理の工程は、産業廃棄物の種類や状態によって次のように異なります。
5-1.燃え殻にして減量
対象:木くずや紙くず、廃油、汚泥、繊維くず
方法:焼却して“燃え殻”にして減量
5-2.砕くことで減容化
対象:廃プラスチック類や木くず、ガラスくず、がれき類
方法:細かく砕くことで、産業廃棄物の容積を小さくする
5-3.溶かして減量化
対象:燃え殻など
方法:1400℃以上の高温で加熱し有機物を燃焼させ、無機物をガラス状にスラグ化
5-4.水分を取り除き減量化
対象:汚泥など水分を含むもの
方法:脱水機を使用し、水分を取り除いて重量と容積を減少
5-5.リサイクルしやすいように選別
リサイクルしやすいように、産業廃棄物を選別するのも中間処理業務の一つ。
対象:紙くずや廃プラスチック類など様々な種類の廃棄物が混じった状態で生じるもの
方法:分別し、適切に処理・リサイクル
6.なぜ、中間処理が必要なのか?
中間処理の目的は、“廃棄物の容量を減量すること”です。
国土の狭い日本では埋め立て施設の数に限界があるため、いかに量を減らすかが重要です。
そのまま最終処分場に埋め立てるのではなく、中間処理にてリサイクルできるものを選別し、焼却や破砕、脱水などを行えば、容量を減らすことができます。
実際に現在の日本では、中間処理を行うことで産業廃棄物の約50%が再利用可能な資源として生まれ変わっています。
しかし、中間処理で廃棄物量を減らしているとはいっても、令和3年度における産業廃棄物の全国排出量はおよそ370,568千トン。
排出量が多いとその分埋め立てるスペースが必要なため、現在日本にある最終処分場はかなり逼迫した状況です。
日本にある最終処分場は全国平均で“あと20年ほどで寿命を迎える”と環境省から発表されているため、今後は廃棄物を排出しないための取り組みやリサイクルをより積極的に行わなければなりません。
参照:令和4年度事業産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(環境省)
7.廃棄物問題の解決に向けて“3R”の徹底を!
以上のように、現在日本は最終処分場の寿命が迫っています。
中には「ごみを埋め立てる場所がないなら、新たに増やせばいい」と考える方もいますが、土地の確保や住民の理解、環境への配慮を考えると新しく最終処分場(埋め立て施設)を新設することは容易ではありません。
この新設には、近隣住民や漁協、水利権などが複雑に絡むため、簡単ではないのが現状です。
しかし、世界がごみで溢れかえる前に最終処分場の使用可能期間をできるだけ延ばすよう取り組む必要があります。
廃棄物の量を減らすためには、今回この記事で取り上げた中間処理はもちろん、私たちが個人で今すぐ取り組めることといえば“3R(リデュース・リユース・リサイクル)の徹底”が大切です。
3Rとは、Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)の総称。
それぞれの単語の意味と求められる取り組みは以下の通りです。
<Reduce>無駄にゴミを出さない
無駄なものや必要ないものを買わない/過剰包装を断る/食品を無駄にしない…etc
<Reuse>何度も繰り返し使用する
不用品は捨てずに知り合いに譲る/詰め替えできるボトルや容器を使用する…etc
<Recycle>ゴミをリサイクルする
市区町村のルールに従いゴミを分別する/積極的にリサイクル製品を購入する…etc
私たちの未来のためにも、処理の流れを知ったうえで私たちにできる身近なところから3R(リデュース・リユース・リサイクル)を実践しましょう!
なお、リダクションテクノでは廃棄物に関する幅広いご相談に対応しています。
廃棄物処理以外にも、リサイクルやコスト削減に関するご提案も可能です。
廃棄物に関してお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
最終処分場(埋立地)の区分・構造について。世界の最終処分場の事情も解説!
産業廃棄物の中間処理はなぜ必要?5つの処理方法や流れについて
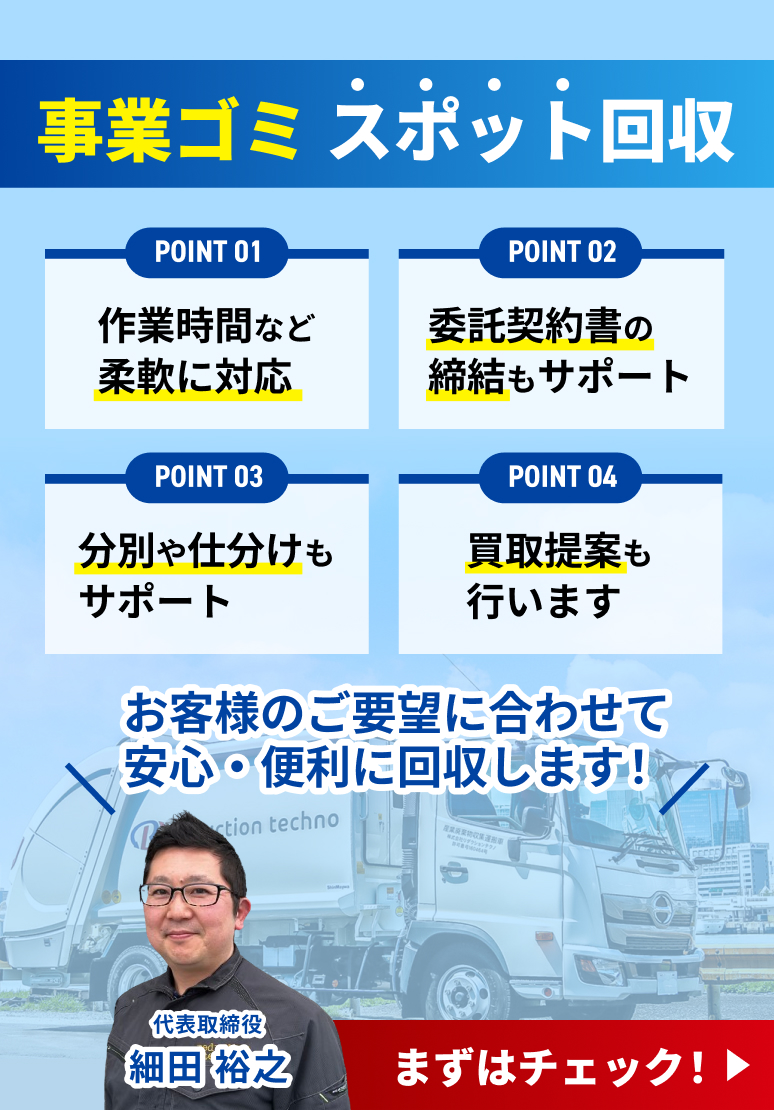
サービス
タグ
- リサイクル
- 環境
- 除菌
- 新型コロナウイルス
- 廃棄物回収
- 使い捨て
- 安心第一
- コンサルティング
- 閉店ごみ問題
- 実地トレーニング
- 有価買取
- 解体費用
- 廃材処理
- 整地
- 価格適正化
- 業者選定
- 低コスト
- 再資源化
- 現場管理
- 緊急
- 業者
- ストレッチフィルム
- ごみ袋
- 再生材ごみ袋
- 環境貢献
- 産業廃棄物
- コンテナBOX
- 2020TDM推進プロジェクト
- LLDPE
- 定期回収
- ルート回収
- 木パレット
- 夜間
- 飛散防止
- 廃棄物
- 輸送貨物事故品
- スプレー缶処理
- 穴あけ作業
- 閉店ごみ
- リニューアル粗大
- 緊急回収
- サーキュラーエコノミー
- ケミカルリサイクル
- マテリアルリサイクル
- サーマルリサイクル
- 輸入食品
- 食品廃棄
- 汚泥
- 建設系廃棄物
- 価格適
- 木くず処分
- 夜間回収
- 不良品
- 在庫品
- グッドデザイン賞
- SDGs
- 廃プラスチック
- 衣類
- 産廃回収
- 医療廃棄物
- バッカン
- 衣服廃棄
- アパレルごみ
- 繊維くず
- 洋服処分
- FUROSHIKI
- ごみ置場
- セメント袋
- がれき類
- レンタル倉庫
- 退去ごみ
- 原状復帰
- トラックターミナル
- Iot
- マニフェスト
- 廃棄物処理法
- 現状回復
- 業態変更
- アパレル
- コンビニごみ
- 機密情報
- 分別
- 食品ロス
- 特定有害産業廃棄物
この記事に関連するコラム
-

産業廃棄物2023.06.05
事業系ごみについて徹底解説!家庭系ごみとの違い、種類・処分方法など
事業活動を行っている方に向けて、この記事では事業系ごみの種類や処分方法について徹底解説! ...
-
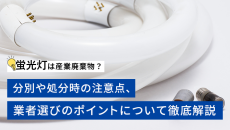
産業廃棄物2020.08.19
蛍光灯は産業廃棄物?分別や処分時の注意点、業者選びのポイントについて徹底...
水銀を含む蛍光灯は、産業廃棄物の混合廃棄物として扱わなければなりません。 また、平成29年...
-

産業廃棄物2022.01.27
燃え殻とばいじんの違いって?燃え殻の具体例や処分・リサイクル方法などを徹...
この記事では、廃棄物を燃やした後に残る“燃え殻”について徹底解説! 産業廃棄物の1つである...
-

産業廃棄物2022.05.02
廃棄物の再委託が禁止されている理由とは?産業廃棄物のみ例外となる場合も!
廃棄物処理法において、廃棄物の再委託は例外を除いて原則禁止されているため注意が必要です。 ...
幅広いご相談に応じます!
- いつでも気軽に相談
- 写真で概算見積もり
- 見積り書もご用意!