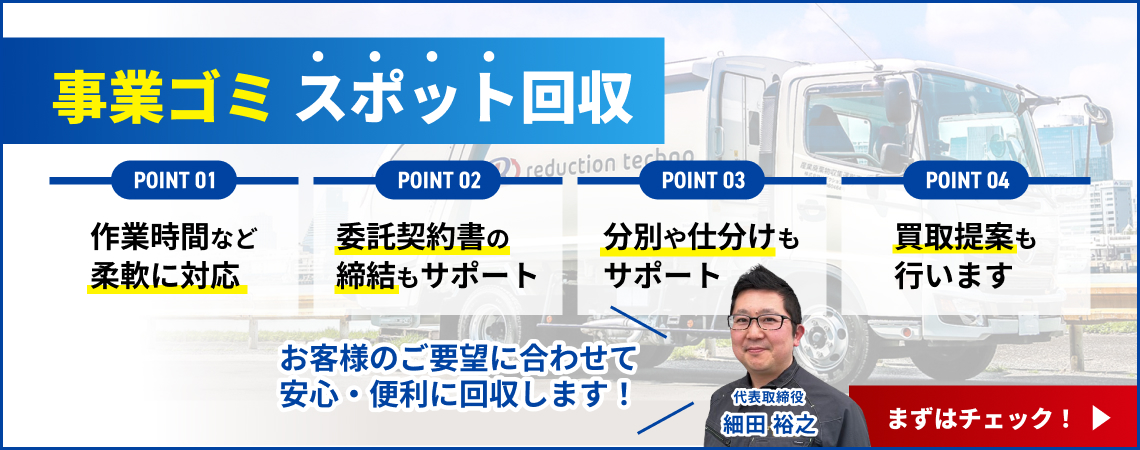コラム
産業廃棄物 2021.08.10
食品リサイクル法について徹底解説!再生利用の優先順位や目標、対象となる食品廃棄物、罰則etc
リサイクル環境再資源化産業廃棄物食品廃棄

食品廃棄物の排出抑制や、食品循環資源の再生利用を促進するために制定された“食品リサイクル法”。 この記事では食品リサイクル法の概要や制定された背景と共に、目標と現状、対象となる食品廃棄物、違反した際の罰則を解説します。 「食品廃棄物の問題を解決するための方法について知りたい」という方や、「食品リサイクルなどに興味はあるが、何から始めればいいかわからない」という方は必見です!
1.食品リサイクル法の概要
そもそも食品リサイクル法とは、製造や卸売など食品関連事業者に食品廃棄物の排出抑制や食品循環資源の再生利用などを促進するための法律です。
正式名称は“食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律”で、2000年に制定されました。
食品リサイクル法では、食品の製造加工業・卸売業・小売業・外食産業などに向けて、食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、食品循環資源の再生利用等を促進するよう呼び掛けています。
参照:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の概要(農林水産省)
2.制定された背景
2000年に食品リサイクル法が制定された主な理由は、近年特に問題視されている“食品ロス”が関係しています。
食品ロスとは、食べ残し・売れ残り・賞味期限切れなどの理由で、まだ食べられる状態の食品を廃棄することです。
食べられる状態の食品を廃棄してしまうことは、ただもったいないというだけでなく、廃棄物量の増加により地球環境にも影響を及ぼすとして世界的に問題視されています。
ちなみに、2023年(令和5年)6月に消費者庁が発表した食品ロス削除関係参考資料によると、2021年における日本の1年間の食品ロスの量はなんと約523万トン!
日本人1人当たりの食品ロス量は1年で約42kgとされており、日本人1人が毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているのと近い量といわれています。
このように食品ロスが深刻化していることにより、状況を改善するために食品リサイクル法が制定されました。
参照:令和3(2021)年度食品ロス量推計値の公表について(消費者庁)
食品ロスとは(農林水産省)
3.再生利用の優先順位・処分方法
冒頭にて食品リサイクル法では食品循環資源の再生利用等を促進するよう呼び掛けていると解説しましたが、食品廃棄物を再生利用する際には以下のように優先順位が設けられています。
発生抑制 → 再生利用 → 熱回収 → 減量
まずは食品廃棄物そのものの発生を抑制し、次の段階として再生利用を実施します。
再生利用には様々な手法がありますが、その中でも次のような優先順位があります。
【優先順位】①飼料化、②肥料化(メタン化発酵廃液等の肥料利用を含む)、③油脂・油脂製品化、④メタン化(発酵廃液を肥料利用しない場合)、⑤エタノール、⑥炭化(燃料および還元剤など)
再生利用が難しい場合は焼却されますが、熱回収も条件を満たせば再生利用として認められます。
【条件】再生利用できる施設が半径75km圏内に存在しない場合、回収される熱もしくは電気の量が1トン当たり160MJ以上(廃食用油は1トン当たり28,000MJ以上)の場合
なお、熱回収が難しい場合は、廃棄物をスムーズに処分できるよう脱水・乾燥・発酵・炭化などが行われます。
4.目標と現状
具体的に、食品関連事業者全体に向けて、以下のような再生利用等の実施率の目標が掲げられています。
【2024年度(令和6年度)までの再生利用等実施率の目標】
食品製造業95%、食品卸売業75%、食品小売業60%、外食産業50%
しかし、現状目標値にはまだ一部達していません。
【2021年(令和3年)における再生利用等実施率状況】 ※2022年(令和4年)発表
食品製造業96%、食品卸売業70%、食品小売業55%、外食産業35%
食品製造業は目標を達成しているものの、食品卸売業は70%、食品小売業は55%、外食産業は35%と、その他の業界は目標を達成できていません。
参照:令和3年度食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率(農林水産省)
定期報告が始まった2008年度と比べれば大きく変化していますが、2024年度までの再生利用等実施率の目標を達成するためには、まだまだ努力が必要です。
4.対象となる食品廃棄物
食品リサイクル法は、全ての廃棄物が対象となっているわけではありません。
食品リサイクル法第二条において、食品や食品廃棄物として定義されているのは以下の通りです。
この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。
2 この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。
一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
出典;平成十二年法律第百十六号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
つまり、対象となる食品廃棄物は次の通りとなります。
■製造工程で発生した食品の加工残さ
■食品の流通過程から発生した売れ残り
■飲食店で排出された調理くずや食べ残し …etc
例えば、一般家庭から排出された調理くずや食べ残しは食品リサイクル法の対象とはなりません。
5.食品リサイクル法の罰則
最後に、食品リサイクル法の罰則をご紹介します。
罰則の対象となるのは、食品廃棄物を年間100トン以上排出している事業者です。
該当する業者は以下のポイントに気を付けましょう。
5-1.報告義務を怠った・虚偽の報告をした場合
・対象事業者は、業種別再生利用等実施率や多量発生者に対する発生量、再生利用量等を報告しなければならない
・報告を怠った場合や、虚偽の報告をした場合は20万円以下の罰金が科せられる
5-2.再生利用等の実施を十分に行わなかった場合。
・対象事業者は、再生利用等の実施を積極的に行わなければならない
・十分に行わなかった場合には、勧告・公表の後、命令が下される
・もし命令に違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられるため注意が必要
6.食品廃棄物の削減・再利用は、環境保全や循環型社会の形成に繋がる!
地球温暖化、資源の枯渇、最終処分場の利用状況の逼迫…etc。
近年では上記のような問題発生により、世界的にもエコな取り組みや環境保全への意識が高まってきました。
いまや循環型社会へ向けた環境への配慮は重視されており、企業の取り組みも評価につながる時代です。
環境保全のためにも企業の今後を考える上でも、廃棄物の排出量削減やリサイクルの推進などといった“循環型社会へ向けた環境への配慮”は欠かせません。
ぜひ、これを機に食品廃棄物の問題や食品ロスの削減についてあらためて考えてみてはいかがでしょうか?
ちなみに、リダクションテクノでは食品廃棄物の処理だけでなく、様々な選択肢をご用意しています。
リサイクルやコストの最適化などのご提案も行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください!
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
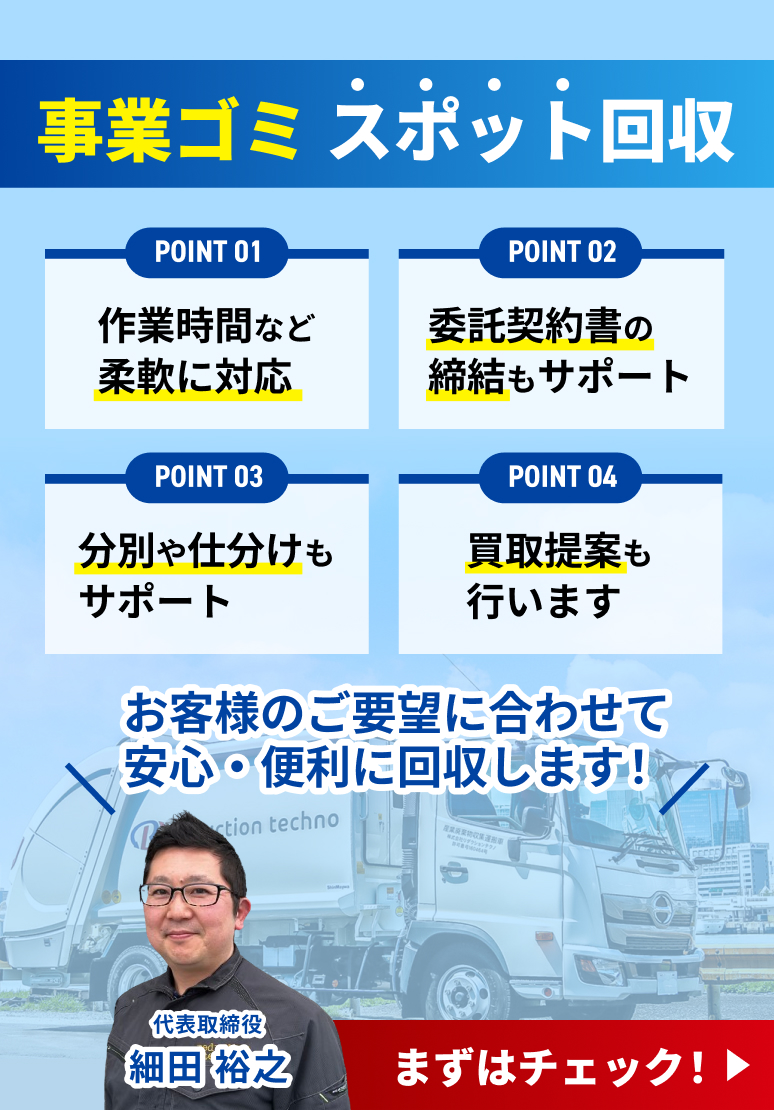
サービス
タグ
- リサイクル
- 環境
- 除菌
- 新型コロナウイルス
- 廃棄物回収
- 使い捨て
- 安心第一
- コンサルティング
- 閉店ごみ問題
- 実地トレーニング
- 有価買取
- 解体費用
- 廃材処理
- 整地
- 価格適正化
- 業者選定
- 低コスト
- 再資源化
- 現場管理
- 緊急
- 業者
- ストレッチフィルム
- ごみ袋
- 再生材ごみ袋
- 環境貢献
- 産業廃棄物
- コンテナBOX
- 2020TDM推進プロジェクト
- LLDPE
- 定期回収
- ルート回収
- 木パレット
- 夜間
- 飛散防止
- 廃棄物
- 輸送貨物事故品
- スプレー缶処理
- 穴あけ作業
- 閉店ごみ
- リニューアル粗大
- 緊急回収
- サーキュラーエコノミー
- ケミカルリサイクル
- マテリアルリサイクル
- サーマルリサイクル
- 輸入食品
- 食品廃棄
- 汚泥
- 建設系廃棄物
- 価格適
- 木くず処分
- 夜間回収
- 不良品
- 在庫品
- グッドデザイン賞
- SDGs
- 廃プラスチック
- 衣類
- 産廃回収
- 医療廃棄物
- バッカン
- 衣服廃棄
- アパレルごみ
- 繊維くず
- 洋服処分
- FUROSHIKI
- ごみ置場
- セメント袋
- がれき類
- レンタル倉庫
- 退去ごみ
- 原状復帰
- トラックターミナル
- Iot
- マニフェスト
- 廃棄物処理法
- 現状回復
- 業態変更
- アパレル
- コンビニごみ
- 機密情報
- 分別
- 食品ロス
- 特定有害産業廃棄物
この記事に関連するコラム
-

産業廃棄物2022.12.26
再生砕石とは?砕石との違いや、再生砕石が使われる場所などを徹底解説!
国から積極的に使用するよう推奨されている資材「再生砕石」。 しかし、中には「再生砕石ってど...
-

産業廃棄物2020.10.20
金属くずは買取りも可能な産業廃棄物!?回収・処分を業者に依頼する際の注意...
産業廃棄物の一つである金属くずは、種類や状態によっては業者に買い取ってもらうことも可能です。...
-

産業廃棄物2022.03.22
コンクリートがらとは?産業廃棄物の「がれき類」と「コンクリートくず」の違...
産業廃棄物の「がれき類」に分類される「コンクリートがら」は、同じく産業廃棄物の分類の1つであ...
-

産業廃棄物2022.10.07
マニフェストが不要なケースとは?産業廃棄物を収集運搬・処分する際の注意点
産業廃棄物を収集・処分する際には、原則として「マニフェスト」という書類が必要です。 しかし...
幅広いご相談に応じます!
- いつでも気軽に相談
- 写真で概算見積もり
- 見積り書もご用意!